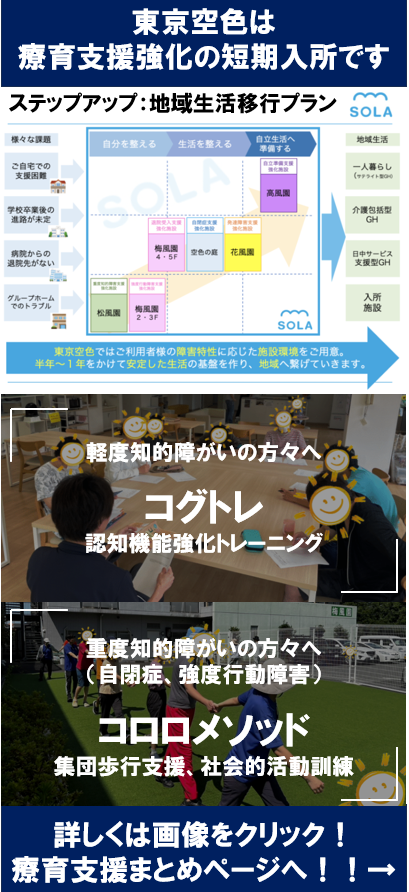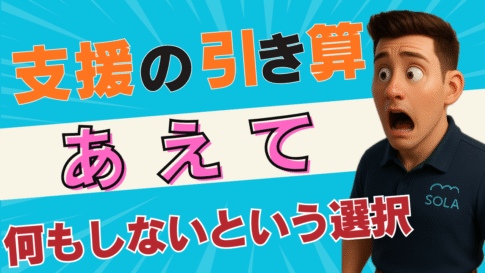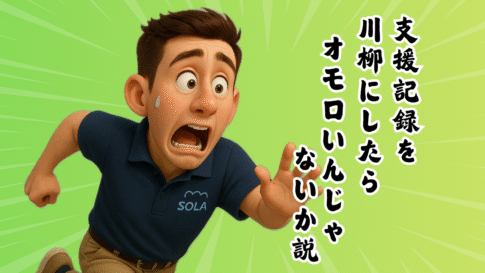こんにちは。東京空色の708(ナオヤ)です。
支援をするうえで、私たちはつい「優しさ」や「寄り添いすぎること」を良しとしてしまいがちです。けれど、目の前の“今”に寄り添うあまり、“数年後”の未来から目をそらしていないでしょうか?
支援者が変わっても、ご本人が穏やかに、そして安心して過ごせるためには──。今回はそのカギとなる「距離感」について、ある事例をもとに考えてみたいと思います。
目次
【事例】Bさんと支援者の「距離」──“優しさ”が生んだ不穏
Before/それまでは
Bさんは、日常生活の中で「困ったら○○さんに聞けばいい」「○○さんなら全部わかってくれる」と、特定の支援者だけを頼るようになっていました。
毎朝の着替え、手洗い、食事の準備。「声かけていいのは○○さんだけ」と他職員の関わりを受けつけず、支援の幅が狭まりつつある状態に。
Intervention/介入
ある日、○○さんが不在の日。支援の流れが変わったことでBさんは混乱し、「○○さんがいい!」と叫びながら居室にこもってしまいました。
その後、数日間は他の職員の声かけにも強い拒否が見られ、「○○さん以外は信用できない」とまで言うように。
私たちはあらためて支援記録を見返し、○○さんがBさんのあらゆる希望に応えていたこと、ちょっとした困りごとも代わって“やってあげる”支援が続いていたことに気づきました。
「自立の芽」を奪っていたのは、もしかすると私たちかもしれない──。
After/その後の変化
関わりを“ほどく”支援が始まりました。「まず自分でやってみよう」と伝え、他の職員が一貫した声かけとサポートを重ねていく。
はじめは怒りや戸惑いを見せていたBさんも、少しずつ「○○さんじゃなくてもできる」「誰に頼ってもいい」と思えるようになっていきました。
今では、複数の職員との関わりの中で、日々を穏やかに過ごせるようになっています。
気づき・学び
「優しくしてもらった」という記憶は、安心感につながる一方で、執着という形で残ることもあります。
支援者の「全部やってあげたい」という想いが、本人の“自分でやってみよう”という力を奪ってしまうことがあるのです。
でも私たちは、今この瞬間だけでなく、数年後・十年後の未来を見据えて支援をしていく存在です。
本人が誰とでも関われること。誰に対しても安心して「助けて」と言えること。それが、私たちが本当に目指すべき支援のかたちではないでしょうか。
支援のヒント:こんな視点が役立ちます
- 「この支援、私以外でもできる?」と自問してみる
- 支援者が“いなくなった後”の未来を考える
- あえて手を出さない=「育くむ支援」という視点
- ご本人の“依存”と“信頼”の違いを見極める
次回予告:「行動の“きっかけ”を探れ──見逃しがちなサインを読む技術」
行動の“始まり”に注目すると、見えてくる支援のヒントがあります。次回は「始まりのサイン」に焦点を当てて掘り下げていきます。
関連記事・内部リンク
※このブログに使用している画像はAIで生成しているものであり、実在する人物ではありません。