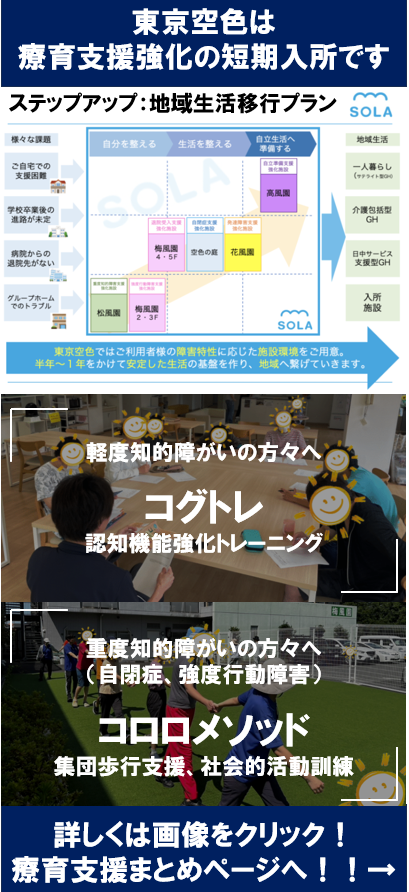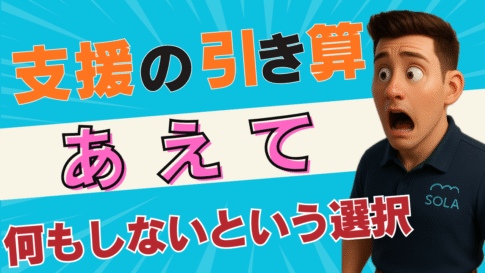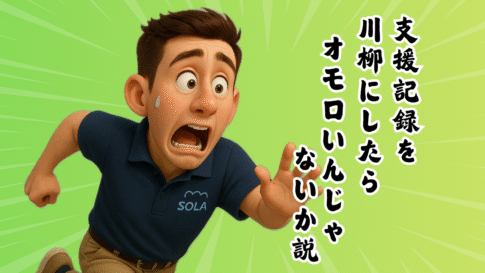“困った行動”に見える背景には、実はその人なりの理由があるかもしれません。福祉支援の現場で必要な「観察力」を事例から学びます。
目次
目次
はじめに──その行動、本当に「困った」?
こんにちは。東京空色の708(ナオヤ)です。
福祉の現場では、日々さまざまな「困った行動」に出会います。
たとえば──
- 朝の準備中に急にどこかへ歩いて行ってしまう
- 集団の中で突然声を上げてしまう
- 支援に入ろうとすると、拒否するように逃げてしまう
こうした行動を前にして、私たちはつい「またか…」「落ち着かないな…」と思ってしまいがちです。
でも、それって本当に“落ち着きがない”のでしょうか?
今回は、「観察力」という支援の土台について、事例を交えながら掘り下げてみたいと思います。
事例:Aさんが音楽を嫌がっていた本当の理由

Before:それまでは
Aさんは、ある活動の時間になると突然耳をふさいで部屋を出て行ってしまうことがありました。
職員の間では「音楽が苦手なんだろう」と暗黙の理解ができていて、Aさんはその時間だけ活動から外れてもよい、という形が習慣化していました。
Intervention:介入
ある日、支援に入った職員が「本当に音楽そのものが嫌いなんだろうか?」と疑問を持ちました。
リビングに設置されたカメラで反応のタイミングを確認し、実際の音の流れと照らし合わせたところ、Aさんが耳をふさぐのは音楽が始まる前──スピーカーの電源を入れた瞬間に鳴る「ボッ」という低いノイズ音の直後だと判明したのです。
After:その後の変化
原因を「ノイズではないか?」と仮説を立て、スピーカーの設定を変更してノイズが出ないように調整しました。
するとAさんは、耳をふさがずにその場にとどまり、音楽が始まっても落ち着いた様子。むしろリズムに合わせて体を揺らすような姿が見られるようになりました。
気づき・学び
もし私たちが「あの人は音楽が嫌いだから」と早々に決めつけていたら、Aさんの「本当は楽しみたい気持ち」に気づけなかったかもしれません。
観察力とは、単に“見る”だけでなく、「なぜ?」と問い続ける姿勢。
その人の中にある小さな“好き”や“苦手”に耳を澄ます力です。
観察力は“特別な力”ではない
観察力というと、経験豊富なベテラン職員しか持っていないスキルのように感じるかもしれません。
でも実は、次のような「ちょっとした視点」で誰でも今日から磨きはじめられます。
- 行動の直前・直後に注目する
- 環境(音・光・温度・におい)の変化を捉える
- 本人の視線・仕草・間に気づいてみる
こうした「気にかける視点」が、行動の意味を少しずつ解き明かしてくれます。
支援の出発点は、「きっと理由がある」という信頼
支援の技術や知識も大切ですが、まず大前提として必要なのは、「この行動には理由があるはず」と信じる気持ちです。
私たちは、本人の“行動”だけを見がちですが、その奥にはたくさんの“物語”が隠れているかもしれません。
観察とは、相手の言葉にならない声を聞こうとする姿勢。
それこそが「人を信じる力」であり、支援の出発点だと思います。
次回予告
第3回:優しさより「ちょうどいい距離感」──関わりすぎない支援の選び方
優しさが裏目に出ることもある? “手を差し伸べすぎない支援”について掘り下げていきます。
← 第1回を読む:「福祉ってなんだろう?ご利用者様との関わりやチーム支援のヒントを探るコラム、はじまります」
※このブログに使用している画像はAIで生成したものであり、実在する人物ではありません。
タグ: #観察力 #支援の気づき #東京空色の支援現場 #708の部屋 #行動の背景を探る #環境調整の視点 #重度知的障害支援 #福祉を目指すあなたへ